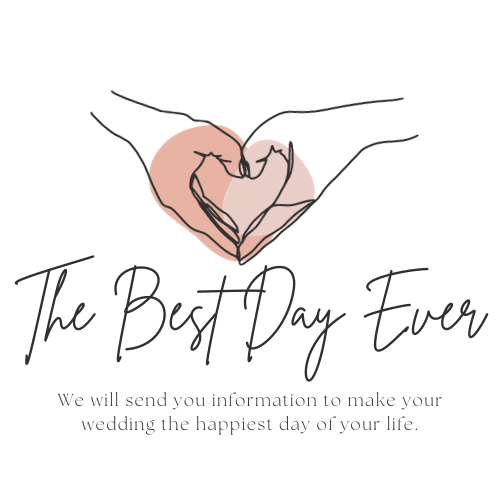ご結婚おめでとうございます!
これから始まる新生活、楽しみなことがたくさんありますよね。
でも、式場探しを始めようとした矢先、雑誌やネットで「平均費用300万円」という数字を見て、急に不安になってしまった方もいるのではないでしょうか。
「貯金がそんなにないし、私たちには無理かも…」
そう感じるのは当然です。しかし、ご安心ください。
その「300万円」を、すべてふたりの貯金から出すわけではありません。
実は、結婚式のお金には「ご祝儀」という強力な助っ人がいます。さらに、プロだけが知っている「正しい節約術」を使えば、満足度を下げずに数十万円単位で費用を抑えることも可能なのです。
この記事では、現役ウェディングプランナーとしての経験をもとに、「みんなが実際に払ったリアルなお金(自己負担額)」と「見積もりを100万円下げるための具体的な方法」を、包み隠さずすべてお伝えします。
まずは一番気になる「本当にかかるお金」の話から見ていきましょう。
結婚式費用の相場はいくら?平均総額と自己負担額のリアル

まずは結論からお伝えします。世の中の「平均総額」を見て落ち込む必要はありません。なぜなら、みなさんが気にすべきは「総額」ではなく「自己負担額」だからです。
多くのカップルの平均総額は約327万円
大手結婚情報誌のデータ(ゼクシィ結婚トレンド調査など)によると、先輩カップルが結婚式にかかった費用の総額は、全国平均で約327万円〜360万円と言われています。
地域による差もあります
- 首都圏: 人数が多く、費用も高め(約350〜380万円)
- 北海道・東北: 会費制が多く、総額は控えめ
- 九州: 招待人数が多い傾向があり、総額も高め
「やっぱり300万円以上かかるんだ…車が買えちゃうじゃん」
そう思いましたよね。でも、ここで計算を止めてはいけません。
実は一番大事な「自己負担額」の計算式
結婚式の費用計画において、最も重要なのが以下の計算式です。これさえ覚えておけば、予算オーバーの不安はグッと減ります。
総額 -(ご祝儀 + 親からの援助)= 自己負担額
結婚式では、ゲストからいただく「ご祝儀」を支払いに充てることができます。つまり、総額からご祝儀を引いた残り(自己負担)だけ用意できれば、結婚式は挙げられるのです。
💰 ご祝儀はいくらもらえる?
一般的に、友人は3万円、上司や親族は3万円〜5万円、近い親族(おじ・おば等)は5〜10万円が相場です。
ざっくり計算すると、「招待人数 × 3万〜3.5万円」くらいがご祝儀の総額目安になります。
【60名招待した場合のモデルケース】
- ご祝儀総額の目安: 約210万円(一人3.5万円想定)
- 結婚式総額: 350万円
- 自己負担額: 140万円
どうでしょうか?
「350万円」と聞くと途方に暮れますが、「ふたりで140万円(一人70万円)」なら、頑張ればなんとかなりそうな気がしてきませんか?さらに親御さんからの援助があれば、持ち出しはもっと少なくなります。
しかし、多くの式場は「前払い」が基本です。「ご祝儀が入る前にお金がない!」という事態を防ぐための資金繰りについては、以下の記事で詳しく解説しています。
👉 【関連記事】貯金なしでも大丈夫?ご祝儀払いや支払いタイミングの裏ワザを読む
結婚式の見積もりが「初期提示」から100万円上がるカラクリ

「最初の見積もりから100万円上がった!」
これは結婚式業界で本当によく聞く話ですが、なぜ起きるのでしょうか?
結論から言うと、最初の見積もりが「最低ランク」で作られていることが多いからです。
契約後にランクアップする項目TOP3
見学時にもらう見積もりは、基本的に一番安いアイテムで計算されているケースが大半です。しかし、打ち合わせが進むと「せっかくだから…」とランクを上げたくなるのが人情というもの。
特に上がりやすいのが、以下の3つです。
これらを合計するだけで、あっという間に50万円、100万円と上がってしまうのです。
契約してから「騙された!」とならないよう、自分の見積もりが適正かどうか、以下のチェックリストで診断してみてください。
👉 契約前なら間に合う!100万円下げる見積もり診断と「鬼の交渉術」
項目別に見る結婚式費用の内訳と節約ポイント

何にいくらかかるのか(内訳)を知っておくと、どこにお金をかけて、どこを削るかのメリハリがつきます。「一点豪華主義」が満足度を高めるコツですよ。
【料理・飲物】ゲスト満足度に直結する項目
- 相場: 一人あたり1.5万〜2.5万円
- ポイント: 料理はゲストが一番楽しみにしているポイント。「ケチった」と思われると満足度が下がるため、あまり下げすぎないのが鉄則。
【衣装・美容】こだわると青天井?
- 相場: ドレス1着 20万〜40万円、タキシード 10万〜15万円
- ポイント: 提携ショップで借りると高いことが多いです。会場によっては、持ち込み料を払ってでも外部の安いドレスショップ(都民共済など)を利用したほうがトータルで安くなるケースもあります。
【演出・ペーパーアイテム】一番の節約のしどころ
- 相場: 招待状 1通400円〜、プロフィールムービー 3万〜10万円
- ポイント: ここは「DIY(自作)」や「外注」で劇的に安くなります!式場に頼むと高いですが、自分でネット注文すれば半額以下になることも。特にムービー系は、最近はスマホで簡単に作れるアプリも充実しています。
👉 プロ並みの動画が6,000円で作れる「Kitto」のレビューを見る
【隠れコスト】遠方ゲストの交通費・宿泊費
見積もりに載らないけれど、意外と大きな出費になるのが「お車代」です。
「全員分出す予算がない…」という場合でも、マナーを守れば半額負担や宿泊費のみ負担でも失礼にはなりません。
👉 意外と見落とす「遠方ゲストの宿泊費」はどこまで負担すべき?
👉 【文例あり】全額出せない時はどうする?お車代の角が立たない断り方
予算オーバーを防ぐ!賢い結婚式節約テクニック5選

ここからは、私がプランナーとして実際に新郎新婦さんにおすすめしている「効果絶大な節約テクニック」を5つ紹介します。
これを実践するだけで、見積もりは驚くほど変わります。
1. 日取り・時期を工夫する(夏・冬・仏滅)
結論、結婚式は「人気のない日程」ほど安くなります。
これらを選ぶだけで、内容は全く同じなのに数十万円安くなるプランがあるのです。「お日柄は気にしないよ」というカップルには最強の節約術と言えるでしょう。
👉 仏滅=不幸は嘘?数十万円安くなる「日取り選び」の正解と2025年カレンダー
2. 持ち込み可能なアイテムをフル活用する
式場で頼むと高いものは、自分で用意(持ち込み)しましょう。
ただし、「持ち込み料」がかかる場合や、そもそも持ち込み禁止の会場もあるので、契約前の確認が必須です。
👉 予算オーバーを防ぐ!持ち込み節約テクニックと削れる項目リスト
3. 「式場紹介サイト」のキャンペーンを使う
式場に直接電話して予約していませんか?それ、実はすごくもったいないことをしています!
「ハナユメ」や「ブラプラ」などの紹介サイトを経由してブライダルフェアを予約すると、タイミングによっては数万円分の電子マネーがもらえたり、サイト限定の大幅割引プランが適用されたりします。
同じ式場でも、どこから予約するかで金額が変わるので、必ずチェックしてください。
👉 見学するだけで4万円?「ブライダルフェア」で特典を二重取りする攻略法
👉 「ブラプラ」は怪しい?Web招待状が無料の理由と持ち込み料をゼロにする裏ワザ
4. クレジットカード払いでポイントを貯める
300万円の支払いをクレジットカードですれば、1%還元でも3万円分のポイントが貯まります。
新婚旅行の足しにしたり、新生活の家電を買ったりできますよね。「カード払いOK」の式場を選ぶのも、賢い節約の一つです。
5. 必要ない演出は勇気を持ってカットする
「定番だから」といって、キャンドルサービスやケーキ入刀をやらなきゃいけないルールはありません。
お金をかける演出の代わりに、「各テーブルを回って写真撮影(フォトラウンド)」をすれば、費用は0円ですし、ゲストとたくさん話せて一石二鳥です。
人数・スタイル別の費用相場シミュレーション

「もっと人数が少ない場合は?」「挙式だけでいいんだけど…」
そんな方のために、スタイル別の相場もご紹介します。
家族・親族のみ(少人数婚)の場合
- 人数: 10名〜30名
- 相場目安: 100万〜200万円程度
- 自己負担: 50万〜100万円程度
派手な演出がいらない分、費用は抑えられます。その分、料理をグレードアップして「食事会」として楽しむ方が多いですね。
👉 10名〜30名の「家族婚」の費用相場と自己負担額シミュレーション
「予算100万円以下」で挙げる場合
貯金がなくても、工夫次第で結婚式は挙げられます。会費制や格安プランをうまく使えば、自己負担ほぼゼロも夢ではありません。
👉 【実例】総額100万円以下で挙げた結婚式の見積もり内訳公開
挙式のみ(披露宴なし)の場合
- 内容: チャペルや神社での挙式のみ
- 相場目安: 30万〜50万円程度
- 自己負担: ご祝儀がないケースが多いため、全額自己負担になることが多いですが、総額が安いので安心です。
👉 食事会なしでも失礼にならない?「挙式のみ」の費用とご祝儀マナー
まとめ:結婚式のお金は「工夫次第」で変わる!
結婚式の費用について解説してきましたが、いかがでしたか?
「300万円」という数字に驚いたかもしれませんが、大切なのは「自己負担額はいくらか」、そして「何にお金をかけて、何を節約するか」というふたりの軸を持つことです。
最後に、これから動き出すふたりにおすすめのアクションをお伝えします。
- まずは「ふたりの貯金からいくら出せるか」を話し合う
- 「ご祝儀の見込み額」をざっくり計算してみる
- お得なキャンペーンがあるサイトからブライダルフェアを予約して、「リアルな見積もり」をもらってみる
まずは実際に式場へ行って、見積もりをもらわないことには始まりません。
以下のサイトなら、見学予約するだけで数万円分のギフト券がもらえるキャンペーンをやっています。使わない手はないですよね!
おすすめの式場探しサイト
▼電子マネーが欲しいなら(キャンペーン充実)
[👉 ハナユメで現在のキャンペーンを見てみる]
※キャンペーン内容は時期により変わります
▼プランナーに直接相談したいなら(手数料無料)
[👉 ブラプラで式場を探す]
▼持ち込み自由にこだわりたいなら
[👉 トキハナで最低価格保証の式場を探す]
賢く準備して、お金の不安をなくし、最高の一日を迎えてくださいね。
応援しています!